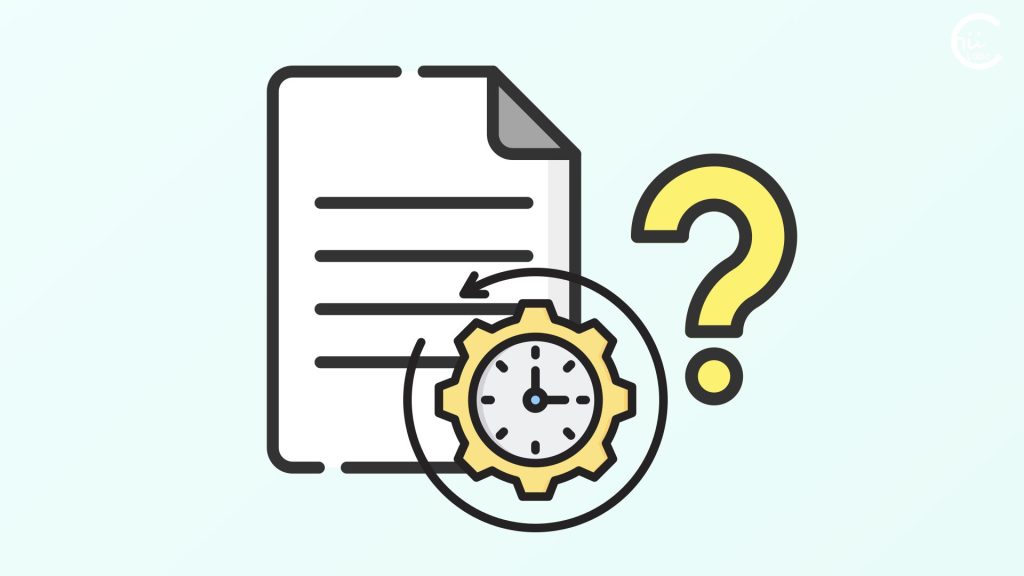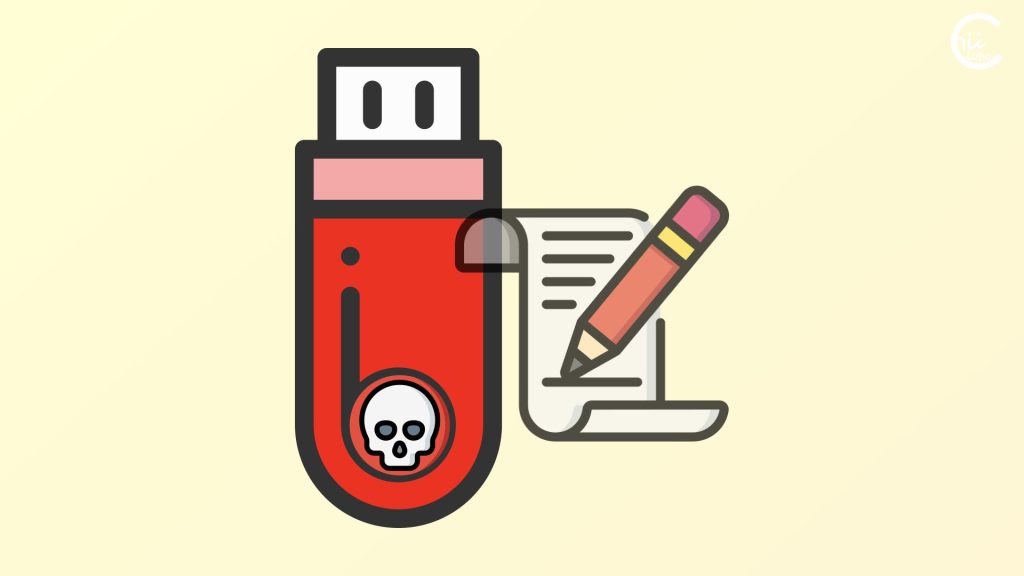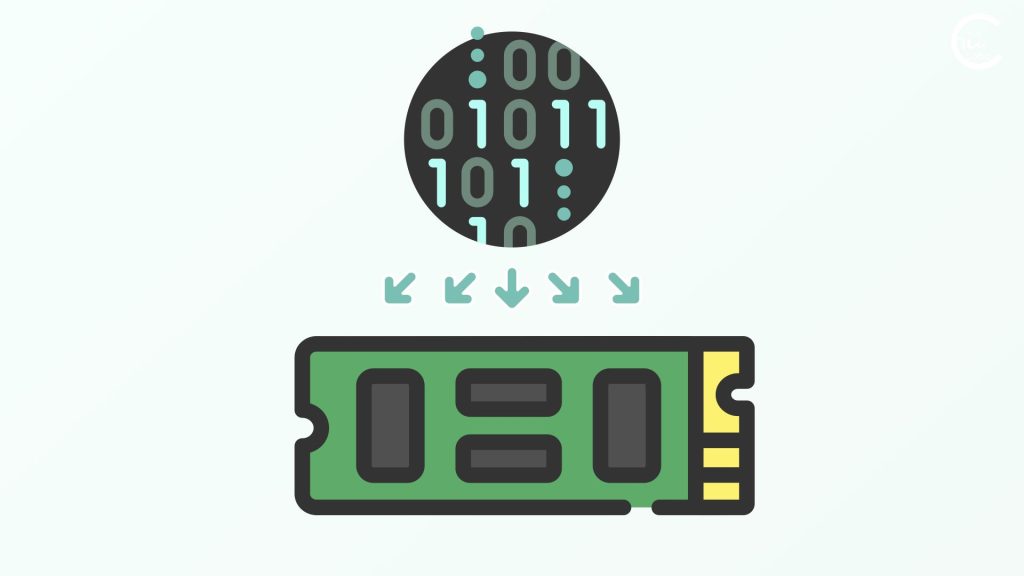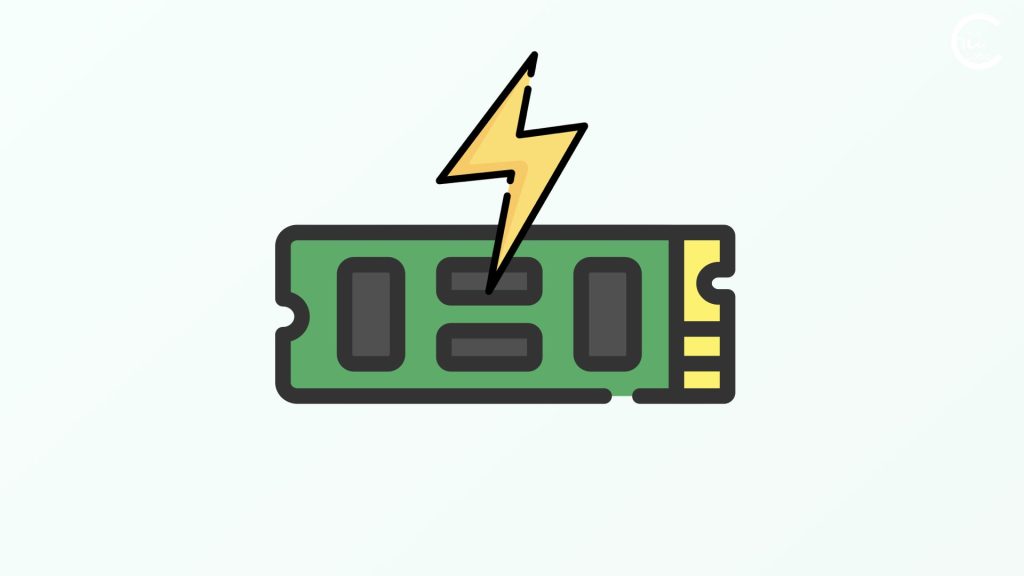- フラッシュメモリは、浮遊ゲートに電子を出し入れして情報を記録する不揮発性メモリです。
- データの書き込みと読み出しは、電子の有無による電流の大きさの違いを利用します。
- トンネル酸化膜の劣化により寿命があるため、ウェアレベリングなどの工夫がされています。
1. フラッシュメモリの基本的な特徴
パソコンのデータ保存などで使う USBメモリやSDカード、SSD。
これらは、「フラッシュメモリ(flash memory)」で情報を記録しています。
フラッシュメモリには3つの重要な特徴があります。
- 電源を切っても情報が消えない性質(不揮発性)
- 情報の書き換えができる
- 書き換え回数には寿命がある
一般的なNANDフラッシュメモリは、約1千回から1万回の書き換えで寿命を迎えます。

電子を操作して情報を保存する、とても賢い仕組みです。
フラッシュメモリ技術は、USBメモリだけでなく、スマートフォンやデジタルカメラなど、多くの電子機器でも活用されています。
2. 「浮遊ゲート」に電子を蓄える
フラッシュメモリには「浮遊ゲート」という「電子を貯める容器」のような部品があります。
データ「0」を書き込む時には、ちょうど容器に水を注ぐように、特別な場所(浮遊ゲート)に電子を集めます。
反対に、「1」として保存するには、容器から水を抜くように電子を引き抜きます。
データの値(0、1)と電子の有無が反対なのは、データの読込みに関係してます。
データの読込みは、「浮遊ゲート」に電子があるかないかを確認します。
「浮遊ゲート」に電気を通すと、すでに電子があると電流が流れにくくなり、電子がないと電流が流れやすくなります。
つまり、この流れた電気の大小で「1」と「0」の情報にしています。
- 制御ゲートとドレインに電圧をかけると、電子が流れ始めます。
この電子の一部が浮遊ゲートに集まり、「0」として記録されます。 - ソースに正の電圧、制御ゲートに負の電圧をかけると、浮遊ゲートにたまっていた電子が引き抜かれます。
電子がない状態が「1」として記録されます。 - 制御ゲートとドレインに電圧をかけて、ソースとドレインの間を流れる電流の大きさを調べます。
浮遊ゲートに電子があれば電流が小さく(0の状態)、電子がなければ電流が大きく(1の状態)なります。
「フラッシュ(flash)」という名称は、ブロック単位での一括消去機能に由来します。
カメラのフラッシュのように、瞬時に大量の消去が行われることから、この名前が付けられました
従来のメモリは1ビットずつ順番にデータを書き換えていましたが、フラッシュメモリは特定の領域(ブロック)全体を一度に消去できる「一括消去」が特徴です。
3. 「トンネル酸化膜」の劣化
フラッシュメモリの寿命の主な原因は、「トンネル酸化膜」の劣化です。
データの書き換えで電子が通り抜けるたびに、「トンネル酸化膜」にはダメージが蓄積していきます。
ある程度ダメージが蓄積すると、電子が漏れやすくなり、電子の出し入れがうまくできなくなります。
情報を保持したり、書き換えたりできなくなるのです。

靴下を何度も履いていると、だんだんヘタっていって穴が空いてしまうような感じです。
このような劣化を遅らせるための工夫として、フラッシュメモリにはデータの書き込み場所を分散させるしくみがあります。
これを「ウェアレベリング」といいます。
![[Windows]「デバイスの書き込みキャッシュ」の有効化とは?](https://chiilabo.com/wp-content/uploads/2025/02/image-6-47-1024x576.jpg)