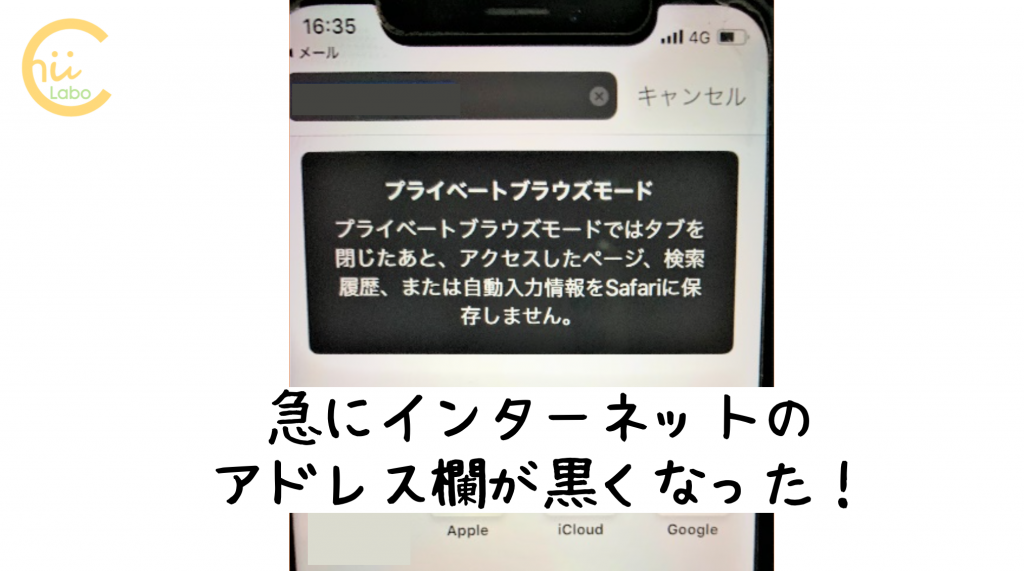Google HomeやAmazon Echoなど、「AIアシスタントとの音声対話で操作できるスピーカー」を「スマートスピーカー」あるいは「AIスピーカー」といいます。
スピーカーといっても、音楽を鳴らすだけではありません。インターネットにつないでニュースや天気を聞いたりするので、どちらかというと「声」で操作できる「ラジカセ」のようなイメージです。
1. 子どもでも操作できるアラーム
そんなスマートスピーカーの機能の1つに「アラーム」があります。
「オーケー、グーグル、5時にアラームをセット」といえば、ちゃんとアラームがセットできます。

Amazon Echoなら「アレクサ、5時にアラームをセット」
これが子どものいる家庭でとても役に立つんです。
大人が「もう5時だからゲームをやめなさい!」と言うより、スマートスピーカーのアラームの方がすんなり言うことを聞くんですよね。
子どもはなかなか集中の切替えが難しいので、大人がいきなり指示しても「えー、待ってよー」などとグズることが多いです。
これまでのちょっとした子育てテクニックとしては、「予告」というのがありますよね。ある程度前もって「あと10分だよ」「あと5分だね」などと予告をすることで、子どもなりに受け止められるようにする方法です。
ところが、スマートスピーカーのアラームだと、一発で切り替えられたりします。
2. スマートスピーカーなら自分でできる
どうして、切替えができるのか考えてみました。
「自分で決めたアラーム」ということが大きいのでしょうか? 自己決定は大事です。スマートスピーカーは子どもでも操作できます。自分で決めた約束は守れることが多そうです。
パソコン・スマホ、あるいはスマートスピーカーと、コンピュータは「誰でも操作できる」方向に進歩しています。パソコンは得意な人や仕事で必要な人に限られていましたが、今のスマホは多くの人の生活必需品になっています。始めは少し慣れが必要ですが、誰かに頼らず「自分でできた!」というのは自信になりますよね。
3. 無機質な声だからこその良さ
あるいは、ツイッターを見ていたら、こんな意見がありました。
子供に「勉強しなさい!」って言いたくないので、今日はGoogle Home に『勉強したほうがいいですよ』って言ってもらったら勉強始まった。
https://twitter.com/kondo_bakusoku/status/1266869409353588737?s=20
スマートスピーカーの声には、子どもなりに人間と違う「客観性」を感じている、のもあるかもしれません。感情のない無機質な声だから受け入れやすいでしょうか。「もう5時だからゲームをやめなさい!」の言い方が、かえって子どもの感情的な軋轢を生んでいたかもしれません。それになんとなく機械・AIだと「間違えなさそう」ですよね。「無感情な伝え方」にも良い面がありそうです。
4. まとめ:AIネイティブの作る社会
これからますますインターネットにつながったAIを利用する機会は増えそうです。子どもの頃からAIに触れてきた人、つまり「デジタル・ネイティブ」あるいは「AIネイティブ」の大人が増えていきますよね。
家庭でのスマートスピーカーの利用を見ると、「これからAIと人間の関わりがどのような社会を作っていくのか」と考えさせられます。
ちなみに、このAIの音声アシスタント機能はスマートフォンでも利用できます。

ホームボタンを長押しすると反応します(機種にもよりますが…)
ということで、今日は「スマートスピーカーの声」のお話でした。
「AIアシスタントとの音声対話で操作できるスピーカー」を「スマートスピーカー」といいます。これまでコンピュータを使えなかった子どもやお年寄り、障害のある人でも操作できるようになり、いろんな使い方が生まれている。