- 一時は台頭した個人ブログですが、いずれ出版業界での「同人誌」のような位置づけになっていくと思います。
- インターネットの歴史を振り返ると、純粋な情報共有の場から始まり、商業化が進むとともに企業ドメインが優勢になってきました。
- インターネットは一般の人が使うものへと成熟し、「なんでもあり」の自由な場所から、権威や規制によって「守られるべき情報空間」に変貌してきているのです。
1. 純粋な情報共有の時代
インターネットの歴史を振り返ると、その役割と情報の量・質が大きく変化してきたことがわかります。
初期のインターネットではアカデミックな情報が中心でした。
次第に趣味の「ホームページ」が登場してきます。
収益化する方法がなかったインターネット初期は、シンプルな情報共有の手段として機能していたのです。

「ブログ」はこのころからありますが、もともとは「ウェブログ」。
つまり、記録をアウトプットする手段として生まれましたよね。
1.1. インターネットの商業化とブロガーの誕生
しかし、インターネットの利用者が増えてくると、企業が参入してきます。
「ドットコムバブル」です。
企業や団体が自分たちの「看板」として、企業サイトを掲載し始めました。
さらに、インターネット上に自社の広告を掲載するようになります。
このような広告主とページ上のスペースをつなぐために、広告ネットワークやアフィリエイト広告の仕組みが整備されます。
すると、個人でもサイト運営による収益化が可能になりました。
「ブロガー」という職業が生まれたわけです。
彼らは、雑記だけでなく、検索ボリュームがあるのに まだ情報が不足している「ニッチ」を探しては、せっせと情報を入れる役割を担いました。
2. 知りたいことは何でも出てくる
情報サイトの収益化が可能になると、企業自体も組織的に情報サイトを作るようになりました。
このようにして情報が集積して、「知りたいことはインターネットにだいたいそろっている」状況になりました。
今となっては忘れられてしまいがちですが、初期のインターネットは図書館よりも情報が少なかったのです。
それが「なんでも出てくる」ようになりました。
2.1. 企業ドメインの台頭と個人ブログの衰退
すると、今度はその正確性や有益性を評価する段階に移行しました。
閲覧者を奪い合う、競争の段階です。
「なんでもあり」では困るので、重視されるようになっているのが「権威性」です。
近年、Google検索が企業ドメインを優遇するようにアップデートされたことで、個人ブログが勢いを失っています。
個人ブログを運営していると、後発の企業ドメインに総取りされた印象があります。
無名の個人にとって、なかなか得難いのが「権威性」だからです。

とはいえ、「企業に比べて個人が仕事を取りにくい」というのは、どんな業界のフリーランスでも一般的な話です。
3. 情報の正確性と有益性の評価フェーズ
情報に対して権威性が重視されるのは、今に始まったことではありません。
書籍出版と同じことです。
実は、書物だって元々は収益化する手段がなかったため、ただの日記や物語から始まっています。
源氏物語や土佐日記などがその例です。
今のようなハードルが生まれたのは、書物を印刷・販売できるようになって商業化したことです。
すると、情報の選別が必要になります。
放っておくと、雑多な情報が溢れ返ってしまうからです。
何が書かれているかも大事ですが、やはり誰が書いたかも重要です。
そして、厳しい編集の目をかいくぐって、やっと出版できるものです。
かつては「リアル」と区別されたインターネット領域は、今は「パブリック」な領域に成熟しています。
3.1. 「質」の担保を求められる
インターネットの情報も「質」の担保を求められるようになったことを示しています。
YouTubeなどのネット動画にも徐々にテレビのような「表現規制」が強まっています。
野放し状態だったネット広告にも、制限する動きが出てきました。
これらは同じ文脈です。
4. ニッチな情報発信と自己表現の場
もちろん、今でも表現の自由はあり、商業誌以外の手段も残されています。
それは同人誌や自費出版です。
同人誌は、特定の趣味やニッチな話題に特化した情報発信の場として機能しています。
インターネットの主要な情報源が企業ドメインに移行しつつある今、個人ブログに残された領域は「同人誌」的な位置づけになるかもしれません。
しかし、それは決して価値が低いということではありません。
個人ブログも、メインストリームから外れた領域なら、独自の価値を提供できます。
大手メディアや企業が扱わないような、専門的な知識や経験に基づく情報発信は、個人ブログならではの強みです。
また、同人誌が創作物の発表の場として重要な役割を果たしているように、個人ブログも自己表現の手段として価値があります。
ブログを通して自分の思いを伝え、共感してくれる読者と繋がることができるのです。

![[Google] 検索結果に「生成AI」の回答が出てくる](https://chiilabo.com/wp-content/uploads/2024/01/image-24-31-1024x576.jpg)

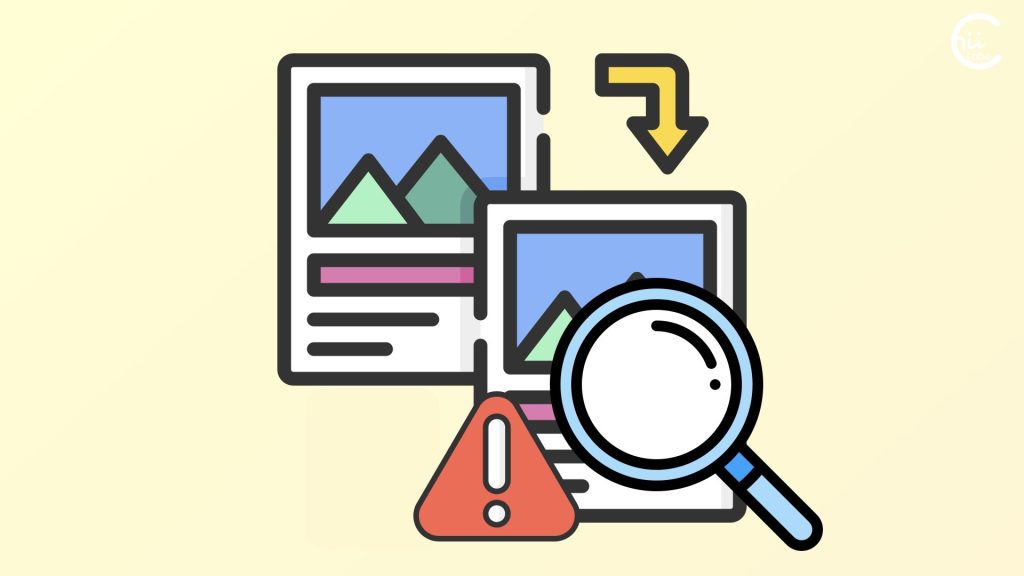


![[mixhost] メーリングリストに配信停止機能を追加できそうにない(mailman)](https://chiilabo.com/wp-content/uploads/2024/04/image-24-15-1024x576.jpg)
![[Cocoon] サイトロゴのリンク先をページ種類で変えた(WordPress)](https://chiilabo.com/wp-content/uploads/2024/04/image-24-27-1024x576.jpg)