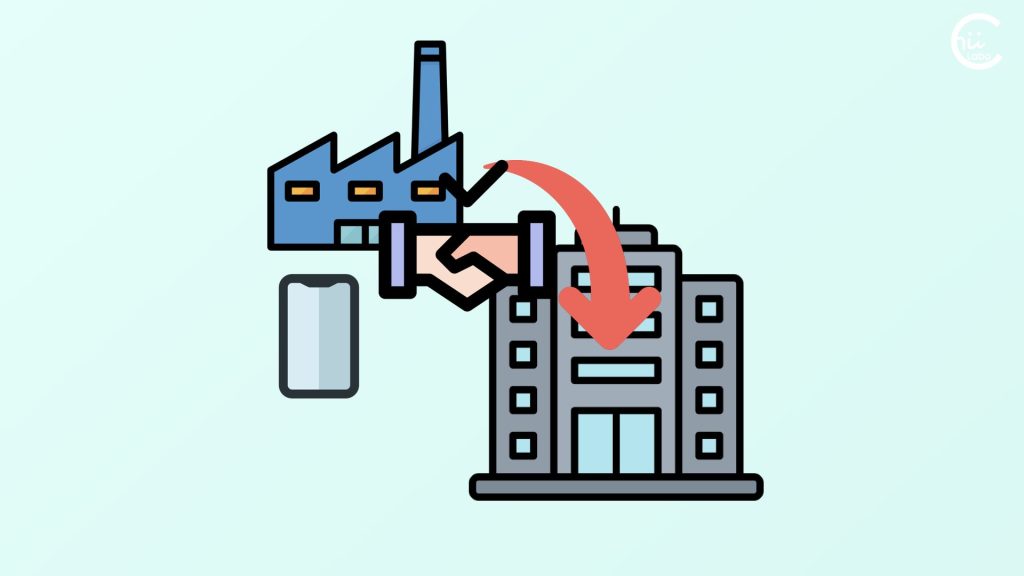- 先日、「らくらくスマートフォンを買ったんだけど、すぐにメーカーが潰れてしまったらしいんだけど」という相談を受けました。
- 正確には、「FCNT株式会社」の「民事再生手続開始」で、2023年5月に公表されていました1。
- その後、2023年10月からは中国のLenovoの出資を得て「FCNT合同会社」として事業を再開しています。
- 現時点では、らくらくスマートフォンなどの製品ブランド・サービスは継続する方針です。

「国産」と思って買っても、使っている間に「外資傘下」になってしまうこともあるのかぁ。
「スマートフォンを作って売る」って、大変なんだね。
1. 富士通からLenovo傘下の「FCNT合同会社」へ
「らくらくスマートフォン」「らくらくホン」といえば、「富士通の製品」というイメージが強いです。

FCNT株式会社は、2016年1月1日に「富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社」として設立していました2。
富士通の事業再編の中で、携帯端末事業が「富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社」、パソコン事業が「富士通クライアントコンピューティング株式会社(FCCL)」として分社化されました3。
その後、2021年4月1日に、「FCNT株式会社」に社名を変えています4。
この社名変更は、富士通グループから離れたためです。
富士通は携帯電話事業から完全撤退し、国内の企業の事業再編・再構築を支援する投資ファンド ポラリスグループの100%出資会社になりました5。
そこで、REINOWAホールディングスという中間持株会社の下で、FCNTは、端末製造を担うジャパン・イーエム・ソリューションズと共通の経営になりました。
しかし、2023年5月、このREINOWAホールディングス、FCNT、ジャパン・イーエム・ソリューションズが合わせて約1431億円の負債により、民事再生法の提要を申請していました。
それを、今度は中国のLenovo(聯想集団:本社 北京)による出資を受けることで、存続することになったようです。
FCNT合同会社はLenovo Group Limited(本社:中国・香港、会長兼CEO:Yuanqing Yang、以下レノボ)の出資を受け、本日、FCNT株式会社からの事業譲受を完了致しました。
事業開始のお知らせ | FCNT株式会社
現時点では、らくらくスマートフォンなどの製品ブランド・サービスは継続する方針です。
長年培ってきたプロダクトのブランド(arrowsシリーズ、らくらくシリーズ)を冠した製品ポートフォリオを維持し、サービス(らくらくコミュニティ等)についても継続して提供いたします。また、修理やOSアップデート等のサポートについても順次再開していく予定です
事業開始のお知らせ | FCNT株式会社
Lenovoは、過去には2005年にパソコンメーカーの IBMを買収しています6。
また、すでに 2017年には「富士通クライアントコンピューティング株式会社(FCCL)」も51%の出資で傘下に収めています7。

「富士通のパソコン・スマートフォン」は、今や Lenovoの傘下なんだね。
2. 「国産スマートフォン」の難しさと「端末値引き」
「大手メーカー」というと「盤石」なイメージです。
FCNTの国内販売シェアは上位5社。
MM総研によると、2022年度のスマートフォンの国内出荷台数に占める割合は8.0%。
半数を占める iPhoneの米アップルを除くと、Androidスマートフォンではシャープ・ソニー・サムスン電子と並ぶシェアを獲得しています。8。

スマートフォン・パソコンの製造においては、最近 国内メーカーの「撤退」が相次いでいます。
2016年にシャープが台湾の鴻海(ホンハイ)に買収された事例も思い起こされます9。
個人向けの携帯電話事業では、京セラも2023年5月に撤退を発表していました。
FCNT株式会社は、2022年3月期に2021年の設立以来 5期連続で赤字を計上していました。
その主な原因として、
- 国内外の同業他社との価格競争
- 携帯電話端末市場の成熟化による売上の停滞
- 2019年10月にスマホの値引きが最大 2万円(税別)までに制限された
- 世界的な半導体不足で原材料費が高騰した
- 円安が進行した
を上げています10。
2.1. 値引きありきの端末価格
このような状況の一因に、通信契約による端末代の大幅値引きと、その規制があります。
2019年10月に改正電気通信事業法が施行され、通信契約と端末をセットで販売した場合の端末値引きを上限 2万円までに制限することになりました。
通信と端末の完全分離や、行き過ぎた囲い込み禁止が目的です。
「携帯ショップでスマートフォンを大幅値引きする」販売促進策が広がりすぎて、短期間で買い替えて転売するような人が出てきました。
その差額は、継続して通信事業者を利用している人の通信料負担になっている点が問題視されたのです。
また、いわゆる「格安SIM」などの新規事業者の参入を促して、通信料の価格競争を進める目的もありました。
端末割引額の上限の根拠とされたのは、購入したスマートフォンを利用している期間に「そのお客さんから見込まれる利益」です。
その範囲であれば、ほかの利用者の負担にはならないと考えられるからです。
見込まれる利益 = 1人ごとの平均売上 × 利益率 × 平均端末利用期間


これって、ある意味 毎月の通信料の前借りのようなものだよね。
ただし、この仕組みは利用期間の途中で、ほかの通信事業者に移ってしまうと帳尻が合いません。
議論の中でドコモは 3万円上限案を主張していましたが、結果としては 2万円に決まっていました。


通信事業者の利益率って、だいたい20%で設定されているんだね。
3. スマートフォンの普及と使用年数の長期化
しかし、この「値引き規制」からスマートフォンの「買い控え」に拍車がかかります。
同程度のスマートフォンでも、値引きがない分だけ「割高」になるからです。
もともとスマートフォンの普及で新しく買う人が減っていましたが、さらに買い替える人も減ったのです。
3.1. すでにほとんどスマートフォン
NTTドコモの「スマートフォン・ケータイ所有動向調査」によると、ケータイまたはスマートフォンを持っている人のうち、スマートフォンの割合は2017年に7割に達しました。
その後も比率はあがり、2023年は96.3%になっています。

ガラケーから新しくスマートフォンに変える、という需要はほとんどなくなりました。

この10年ほどで、すでに携帯電話を利用している人はほとんどスマートフォンに移行したんだね。
いま、新しくスマホを買う人は中高生ぐらいなのかな。
3.2. 買換サイクルが長くなる
一方、スマートフォンの買換サイクルも長くなっています。
内閣府の「消費者動向調査」によると、2022年のスマートフォンの平均使用年数は 4.6年(2022年)。
2010年から2017年までは おおむね 3.6年ぐらい11で推移していました。

買換サイクルが 3.6年→4.6年に伸びるということは、単純計算でその年に買い替える人は78%(3.6÷4.6)になります。
そこに来て、「半導体不足」「円安」などによる原材料費の高騰。
結果として「携帯電話やスマートフォンはタダ同然で機種変更できる」という状況が長く続いたことにより、製造費用に見合った価格であっても以前ほどは売れない状況になってしまっているのです。

ケータイ時代の2年ごとに「0円」で機種変更できたのも「異常」だったのかもね。
廉価版のスマートフォンでなければ、4年ぐらいなら多少遅くなるけど使えるよね。
このようなスマートフォン・メーカーの苦境を受けて、端末割引額の上限は最大4万円に緩和される方向で議論されています。



(補足)
- 民事再生手続開始の申立て及びスポンサー支援に係る意向表明受領のお知らせ | FCNT株式会社
- お知らせ・プレスリリース 2016年 | FCNT株式会社
- 会社分割(簡易新設分割)による子会社設立に関するお知らせ : 富士通
- 社名変更のお知らせ | FCNT株式会社
- 携帯端末事業の再編に関する株式譲渡契約の締結について : 富士通
- 日本IBMのPC事業を引き継いでレノボ・ジャパンが始動 – ITmedia NEWS(2005年05月02)
- Lenovoが富士通のPC事業を支配下に。FMVブランドはNECに加え継続 – PC Watch
- 国内シェア3位、「らくらくホン」のFCNTが1431億円の巨額負債で経営破綻 | 日経クロステック(xTECH)
- シャープ経営悪化で鴻海が突き付けた「経営陣交代」。様変わりした「蜜月」関係のゆくえ | Business Insider Japan
- 「arrows」「らくらくスマートフォン」など展開、FCNT(株)ほか2社が民事再生 負債は保証債務を含めて3社で2087億円(東京商工リサーチ) – Yahoo!ニュース
- ケータイの買い替えサイクル長期化――2010年度には3.6年に – ITmedia Mobile